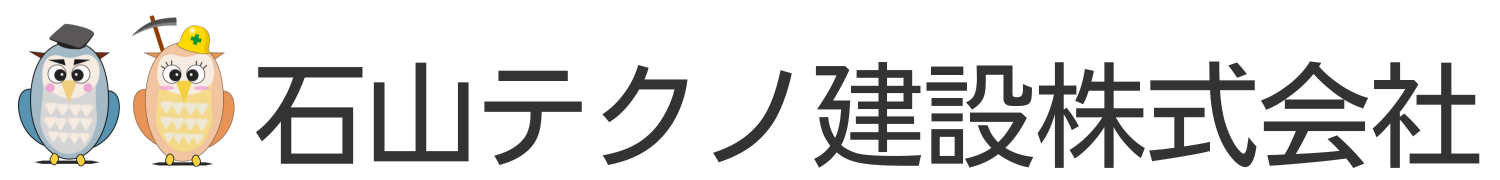京町家に新しい風を吹き込んだリノベーション

京町家に新しい風を吹き込んだリノベーション
婆娑羅金木犀

DETA
場所:京都市 上京区
建築年月:1935 新築
構造:木造/伝統工法
階数:2階建て
利用目的:ゲストハウス
お施主様との出会い
亀岡の古民家を紹介したyoutubeを見ていただいたのがきっかけです。
お施主様のご希望
施主である実業家の方は、「京都の文化を残したい、そして伝えていきたい」という熱い想いをお持ちでした。
そして、西陣の京町家をリノベーションし、文化体験の拠点となる簡易宿泊所として活用したいという、明確なビジョンを描いておられました。
一方で、ご自身が実際にこの京町家で暮らすなかで感じた、「京都の夏と冬の厳しさ」や「前の通りの音の気になりやすさ」、「蚊やゴキブリ、小動物などへの不安」、そして「急な階段の上り下りのしづらさ」など、京町家特有の悩みにもきちんと向き合っておられました。
そのうえで、これらの課題にも丁寧に配慮してほしい、というのが施主のご希望でした。

コンセプト
今回のリノベーションでは、「京町家らしさ」と「これからの京町家」という、ふたつの想いを大切にしながら計画を進めました。
まず、「京町家らしさ」とは、長い時の中で自然と宿ってきた美しさや気配のこと。
具体的には、日々の暮らしの中で育まれる「躾(しつけ)」、細やかな装いや設えとしての「飾」、職人たちの繊細で確かな「匠」の技、そして自然素材が醸し出す温もりや質感としての「材」、こうしたものの積み重ねが、京町家の魅力そのものだと感じています。
この“らしさ”を大切に守るために、私は「オーセンティシティ(authenticity)」と「インテグリティ(integrity)」というふたつの言葉を意識しました。
オーセンティシティは、「ありのままに、飾らず本物であること」。
インテグリティは、「ごまかさず、誠実であること」。
その精神を、設計や素材選びのひとつひとつに込めています。


一方で、もともとの京町家にはなかったけれど、「京町家らしさ」として人々がイメージする要素も、今回はあえてアイコン(icon)として取り入れました。商業的な視点も持ちつつ、“らしさ”を感じられる工夫です。
そしてもうひとつの柱、「これからの京町家」。
これは、町家をこれからも残していくための、新たなかたちへの挑戦でもあります。かつては「住む町家」として使われていた建物を、現代では「住まない町家」、つまり文化体験の場や宿泊施設など、用途を変えて活かしていくという考え方です。
この考えのもとに意識したのが、「リビング・ヘリテージ(living heritage)」という考え方です。
それは、歴史ある建物の「躾・飾・匠・材」を尊重しながら、今の暮らしや技術に合わせて活かし続けていくこと。
使い続けることで、町家の魅力を次の時代へとつないでいきたい、そんな想いを込めています。

調査

ご購入の際に、既存住宅状況調査(インスペクション)を受けておられましたが、さらに安心して改修を進めるために、実際に工事を担当する小川棟梁にも、屋根や床下の状態を詳しく調査していただきました。
その結果、建物の状態は良好で、大きな問題がないことを確認しています。

ポイント解説
「ケ」と「ハレ」が同居するオトリニワ


もともとトオリニワは、勝手口や家事スペースなど、暮らしの中の「ケ」の機能を担う場所です。
けれど、この空間ではそれだけでなく、吹き抜けの開放感を活かした「ハレ」の場としての役割も持たせています。
「ケ」と「ハレ」が同居する――そんな施主のユニークなアイデアに、最初は少し戸惑いもありました。ですが、「ケ」の部分は大きな棚の中にすっきりと収めることで目立たなくしつつ、ガラス戸と石畳、そしてLEDの光で「ハレ」空間の連続性を演出。
ふたつの役割を、ひとつの空間の中で調和させることを試みました。
人がつながるオモテノマ


門をくぐってすぐ横にあるのが、「オモテノマ」です。食事をしたり、人を迎えたり、みんなで集まったりと、いちばん“動き”のある空間として、庭とのつながりも意識しながら設計しました。
あえて野趣ある梁を見せ、床にはチーク材のヘリンボーン貼りでリズムをつけています。さらに梁には朱色の「縄がらみ」を施し、印象的なアクセントに。
また、施主ご自身が見つけてこられた長い踏み石が、ゲンカンニワとの一体感を生み出してくれています。細部にまでこだわった、迎える場にふさわしい空間です。


お座敷はもっと京町家らしく。




1階と2階にはそれぞれ座敷がありますが、どちらもほとんど手を加えず、「ありのまま」の姿を大切に残しています。あえて手を入れる空間と、あえて触れない空間を明確に分けることで、「京町家らしさ」がより際立つように設計しました。
少しだけ補足すると、実は床の高さを調整するために、見えない床下ではしっかりと工事を行っています。そういう意味では、「何もしていない空間」というより、「手跡を見せない空間」と言うほうが、正確かもしれません。

むかしと現代の職人技が、表情豊かに共演する板間


対照的に、2階の板間は、より大胆な改修を行いました。
畳だった床はチーク材に張り替え、天井は高く、間仕切りも取り払って、ひとつの大きな空間へと生まれ変わらせています。


天井裏から現れた野材の梁は、想定通りのものでしたが、思いがけない発見もありました。
それが、枠釣や名栗(なぐり)仕上げの桔木(はねぎ)です。丁寧に磨き直し、新たな命を吹き込むことで、空間により豊かな表情を与えてくれました。
一方で、土壁の小壁は、欄間や下地窓とともにあえて残し、かつてこの町家を手がけた職人たちの丁寧な仕事と調和するよう配慮しています。
それに呼応するかたちで、それ以外の壁は、落ち着いた風合いの珪藻土クロスでまとめ、全体のバランスを整えました。

主寝室の小上がり


「京町家らしさ」のひとつでもある板間の空間に、あえて介入するかたちで、小上がりを設けました。
これは、「これからの京町家」としての新たな提案でもあります。
仕上げや素材には、「ごまかさない」ことを大切にし、あえてコントラストをつけることで、空間の違いが引き立つよう工夫しています。
たとえば、壁は真壁に対して大壁、床は板に対して畳、木材は古色に対して白木と、意図的に対比をつけました。
また、当初は天井を設けずに「解放感」を大切にしていましたが、完成後に「少し落ち着かない」との声があり、最終的に桧のルーバーを増設しました。
このルーバーの設計には、LiDARによる3D計測を行い、その空間データ上でルーバーをモデリングして「見える化」することで、完成形をイメージしながら丁寧に検討を重ねました。


照明による空間の演出


近代建築としての側面も持つ京町家には、すでに電気が引き込まれており、職人の手による「照明器具」が、昔から空間の中に自然に溶け込んでいました。
今回の改修では、そうした照明器具を京町家のアイコンのひとつとして活かしつつ、新たに導入した照明は、LEDによる建築化照明としています。器具そのものは見せず、光だけを空間に溶け込ませる手法です。


コンパクトなLEDの光は、「躾」「飾」「匠」「材」といった京町家の本質にそっと寄り添いながら、新たな価値をそっと添えてくれる――そんな存在であると考えています。
窓から生まれる、暮らしやすさ


断熱性や防音性を高めるには、建物の中でも特に弱い部分である「窓」を見直すことが効果的です。
1階の縁側とオモテノマの窓には、Low-Eペアガラス(5+3mm)を採用。さらに、左右の窓をはめ殺しとすることで隙間を減らし、剛性も高めています。
また、宿泊施設としての安全性にも配慮しています。
火災時に求められる排煙のための開口部として、縁側の欄間は引き込み窓や回転窓に改修。
さらに、小上がりの上部にも外倒し窓を新設することで、排煙口としての役割を持たせています。
快適さと安全性、そして美しさのバランスを大切にしながら、細部にまで丁寧に工夫を重ねました。


泊まって体感するリノベーション
こちらの京町家に実際にお泊まりいただけます。
古き良き意匠と現代の快適さを両立させた空間を、ぜひご体感ください。

施工事例をもっと見る


お問い合わせはこちら

石山テクノ建設が再生した京町家に、実際にお泊まりいただけます。
木のぬくもりや光の入り方、静かな時間の流れを感じながら、
京都の暮らしを体験してみてください。